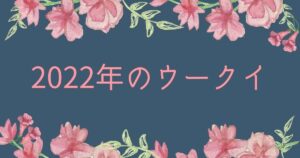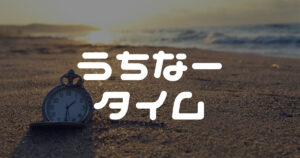当ブログ沖縄Seisaでは、沖縄県内の沖縄そば屋さんの紹介もしていますが、今回はその『沖縄そば』の由来・歴史を紹介します!
沖縄そばとは
沖縄そばとは、小麦粉を原料にした麺をカツオ・トンコツ・塩・昆布などの出汁で作ったスープに入れていただく沖縄の伝統料理のひとつです。当然、それぞれの沖縄そば屋さんや家庭で味付けも異なってくるのですが、基本的には下記のような原材料から作られています。
<麺の原材料>
- 小麦粉
- 塩
- かん水
- 木炭 など
<スープの代表的な原材料>
- カツオ節
- トンコツ
- 塩
- 鶏
- 昆布 など
<トッピング具材>
- 三枚肉
- ソーキ
- なんこつソーキ
- てびち
- スーチカー(豚肉の塩漬け)
- 中味(豚のモツ)
- ゆし豆腐
- 卵焼き
- ネギ
- かまぼこ など
<調味料(お好みで)>
- 紅ショウガ
- 七味唐辛子
- コーレーグース
- ヨモギ(少数派)


沖縄そばのルーツ
ルーツは中国
沖縄そばは、琉球王朝の時代である15世紀頃から存在しているといわれています。日本でラーメンが食べられるようになった時代よりもずっと昔なんですね!
それだけ昔のことなので、沖縄そばのルーツには諸説あり、明確にされているわけではありません。どちらにせよ、14世紀後半~15世紀にかけて中国(明や冊封使)からもたらされたという説が有力です。
※ただし、沖縄そばが庶民にまで広まったのは明治後期頃からです。

沖縄の伝統的な菓子「サーターアンダギー」と同じく、やはりルーツは中国で、琉球王国時代の中国との貿易交流の親密さが伺い知れますね。

「沖縄そば」の名称の歴史
明治後期には、那覇市に初めての庶民向けのそば屋さん「支那そば」が開店したのだそうです。それから、庶民向けのそば屋さんは沖縄県内各地に徐々に増えていきました。
なお、「支那そば」で提供されていた沖縄そばは、「唐人そば」と呼ばれる醤油ベースの黒いスープのそばだったそうです。


戦後になると、米軍から配給される小麦粉を使って沖縄そばを提供するお店が急速に増えていきましたが、本土復帰の1976年、公正取引委員会は蕎麦粉を使っていないにも関わらず、「沖縄そば」と名乗っていることを問題視します。「そば」の定義は、「蕎麦粉を30%以上使っていること」という規約があったからです。
当時の沖縄製麺協同組合は、沖縄県民に愛される「沖縄そば」の名称を何とか守ろうと、東京本庁へ出向き必死の交渉を続けます。

そして、、1978年10月17日、約2年に渡る交渉の末、ついに公正取引委員会は「本場沖縄そば」の名称を使用することを認可したのです!
沖縄では、毎年10月17日は「沖縄そばの日」として県内各地でイベントが行われたり、スーパーでセールが行われますが、このような背景があったんですね!
先人たちの気概と努力、そして公正取引委員会の柔軟な英断にも感謝です。


沖縄そばの特徴
蕎麦粉は未使用
有名なお話(と思ってます)ですが、沖縄そばの麺には蕎麦粉は使われていません。
その理由は、前述の通り、沖縄そばのルーツは中国とされており、小麦粉から作られる「中華麺」の製法と似通っているためと考えられます。
太目の麺
沖縄そばの麺は、「細麺」「太麺」「平麺」など種類は様々ですが、総じて蕎麦麺よりも太目です。そしてほとんどの場合、断面は円形ではなく、やや平らになっています。


地域別の特徴
宮古島の宮古そば
宮古そばとは、沖縄県の宮古島発祥の沖縄そばで、あっさり目のスープと縮れのない細い平麺を使っていることが特徴です。そして、本来は三枚肉やかまぼこなどの具材は、麺の下に隠す風潮があったようです。
※現在の風潮は未調査です。。
八重山の八重山そば
八重山そばとは、沖縄県の八重山発祥の沖縄そばで、トンコツベースのスープを基本として、縮れのない細い麺にウコンなどを使い黄色く着色していることが特徴です。